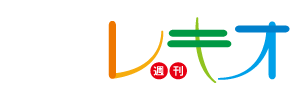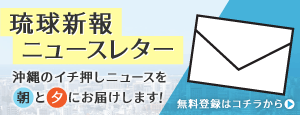健康な生活習慣の礎に。
無理なく続ける健康体操

「日本最初の健康体操」とされる自彊術。体の各部位をたたく、ひねる、伸ばすなどを組み合わせた31の動作で構成され、シンプルでわかりやすいのが特徴だ。健康づくりや生活習慣の改善、ストレス解消に役立てようと、県内各地にも愛好者がいる。自彊術歴40年以上となる指導者・東安子さん(88)の教室を訪ね、その魅力や効果について聞いた。
那覇市の壺屋児童館で毎週火曜日に行われている東安子さんの自彊術(じきょうじゅつ)教室。開催日に訪ねると参加者たちが車座になって「いち、に、さん、し」と声を出しながらリズミカルに体を動かしていた。
参加者のほとんどは70代の女性。毎回10~20人程度が参加するという。長年続けている人が多く、前屈や開脚などの動作がスムーズで柔軟であることに驚かされる。講師の東さんに至っては、前屈の際に手首が足先よりも前に出るほどの柔らかさ。片足立ちや腕立て伏せも難なくこなしている。

自彊術との出合い
自彊術の始まりは1918年(大正5年)。東京・両国であんまやマッサージを行っていた中井房五郎が考案した。当時の実業家・十文字大元の病気を治療した中井の技を基に作り出された体操であるという。名称は中国の古典『易経』の一説、「天行健、君子以自彊不息(テンコウケンナリ、クンシハミズカラツトメテヤマズ)」から取ったもの。じょうず、へたではなく、自分の意思で毎日続けることこそ重要と説いている。
東さんは自彊術を始めて40年以上。リウマチを患い、手術と入退院を繰り返していた時に、公益社団法人 自彊術普及会の第2代会長で医師の故・近藤芳朗さんの講演を聞いたことがきっかけだった。

当時沖縄では自彊術を学べる場所はなかったが、講演会を聞き、心身の健康を手に入れたいという有志が集まったのだという。東さんは東京にも足を運び、その動きを学んだ。自彊術普及会沖縄支部の立ち上げにも尽力し、東さんの夫、故・清志さんは初代会長も務めた。
自彊術を継続して行ったことで東さんのリウマチの症状は改善。車椅子生活のリスクもあった状態から健康を取り戻した。
「現在は変形も止まり体もぴんしゃん!ハンドルを握って運転もできます。少しは効果あったんじゃないかね(笑)」
冗談めかしながら、笑顔で話してくれた。
自分のペースで
東さんの教室では、まずは座りながらの柔軟体操、その後、自彊術の31の動作に入る。自彊術の動作では、はずみをつけて動くこと、呼吸や掛け声を意識することも大事とされている。
「キツいと感じる動きは途中で止まってください。無理しないで」
自身も体を動かしながら参加者たちにそう声をかける東さん。個々人のペースややる気を尊重することも自彊術ならではの考え方だ。また、体操の合間や教室の最後には、「大切なのは食生活と運動のバランスですよ」と念を押すことも欠かさない。

「昨年は腰の手術をして2カ月入院したんだけど、また戻ってきて続けているよ」
そう話してくれたのは、参加者の松堂静子さん。東さんの教室に通うようになって22年目。自彊術は大切な生活の習慣となっているようだ。参加者同士も仲が良く、にこやかにおしゃべりしながら、お互いの体調を気遣っている。長年通う人が多いのは、自彊術の効果もさることながら、教室の和やかな雰囲気も一役買っているのかもしれない。
東さんが講師を務めるのは壺屋児童館の教室(毎週火曜10時15分~)とウエル・カルチャースクールで開講している2クラス。この他、県内各地の自治体などでも健康講座として教室が開講されている。自彊術は、柔軟や体の動作に自信がない、という人にも継続しやすくおすすめだ。
(津波典泰)
(2022年10月20日付 週刊レキオ掲載)