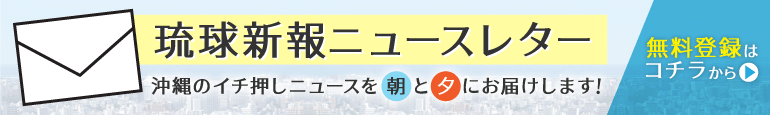裁判の公正さを保つため、司法権はあらゆる権力の干渉を排し、独立していなければならない。議会、政府などから圧力があっても一切、判断を左右されず、裁判官は独立してその職権を行使する。司法権の独立は近代国家で制度的に確立しているはずだ。
1959年の日米安保条約改定時に、司法権の独立がないがしろにされ、米側に便宜を図る動きがあったことが明るみに出た。
米軍の旧立川基地(東京都)にデモ隊が入り込んだ砂川事件で、米軍基地の存在を違憲とする無罪判決が下された後、当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米首席公使に会い、大法廷の評議方針や公判日程を伝えていた。
布川玲子元山梨学院大教授が機密を解かれた米外交文書を入手し、憲法や裁判所法に抵触する驚くべき事実が分かった。
マッカーサー駐日大使から米国務長官に送られた秘密公電によると、大法廷の公判日程が決まる3日前に田中氏は「最高裁判決は恐らく12月だろう」と述べていた。
さらに「結審後の評議は実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶりかねない少数意見を回避するやり方で評議が進むと願う」と語っていた。少数意見を出さずに1審を破棄し、「合憲」判決を示唆する発言に間違いなかろう。
60年の安保条約改定を控え、米側は強まる反対世論に神経をとがらせ、最高裁ができるだけ早く基地の存在を合憲とする判決を下すよう、圧力をかけていた。
「法の番人」であるはずの最高裁の長官が、米国による司法介入を許す隙を見せ、裁判の当事者よりも前に公判期日を漏らし、評議の秘密を自ら破っていた。
田中長官のあまりに卑屈な対米従属姿勢は、沖縄県民の基本的人権と平穏な暮らしを脅かす米軍基地のありようの源流の一つであり、今に続く現在進行形の問題だ。
嘉手納、普天間の両基地をめぐる爆音訴訟で、裁判所は安保条約に基づいて駐留する米軍機の運用を制限できないとする「第三者行為論」を盾に、米軍基地の運用に口を挟もうとしない。米兵事件の起訴率の低さも歴然としている。
基地被害に苦しむ住民の救済に背を向けた司法の姿は、その独立を放棄した当時の最高裁の姿勢と64年の時を超えて結び付いている。対米従属の闇の深さに暗然とする。