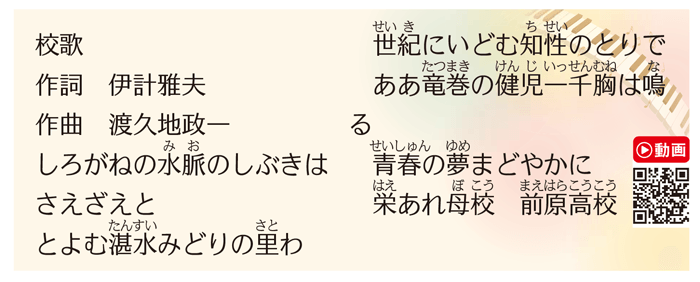日本舞踊家の若柳賀寿乃(78)は前原高校の17期。体育教師との出会いを通じて、舞踊の基礎を学んだ。

1944年、具志川村(現うるま市)川崎で生まれ、大勢のきょうだいに囲まれて育った。家計を助けるため新聞配達に励んだ。
川崎小中学校に通っている頃から踊りが好きだった。「踊っていたのは日舞ではなく洋舞。学芸会の時はクラスの代表として踊っていた」
59年、前原高校に進む。入学時の面談で「歓送迎会で踊ってほしい」と依頼された。演目は中学時代のレパートリーだった「桑港(シスコ)のチャイナ街(タウン)」。学芸会で踊る若柳を見た前原高校の教諭がいた。新入生なのに、いきなり舞台で踊った。
入学時はバレー部で活動し、その後は手芸クラブに移った。ダンス部には所属しなかったが、踊りやダンスを披露する機会はあった。2年になった若柳は体育教諭の新垣幸子に声を掛けられる。体操部のメンバーと共に前原高校の代表として中部農林高校の体育祭で踊ってほしいという。
「新垣先生から『一人だけ目立ってはいけない。バレエのプリマじゃないのよ』と言われながら一対一の特訓を受けた。現在の私の素地は、この時つくられた」
62年に卒業後、東京の専門学校に進み、都内の企業で経理職に就く。その頃から日舞と和装を学ぶようになる。72年に帰郷し、若柳賀寿乃日舞研究所を開設。現在、沖縄日本舞踊協会長を務める。
高校時代の写真を収めたアルバムが手元に残っている。「男女の仲が良かった。『写真を撮るよ』の合図で皆が集まった」と若柳は懐かしむ。
思い出が詰まったアルバム。若柳は学びやを巣立つ決意と友への思いを込めた言葉を添えた。
「忍耐とは希望を持つことの技術である」
「花は散っても友は散らず」

声楽家の泉惠得(74)は21期。芸大を目指して歌い、夜通しピアノを弾く高校生だった。「音楽一筋。必死だった」
1947年、平安座島で生まれた。島にやってくる劇団の芝居を楽しむ少年だった。「ガキ大将の私は子分を集めて、島にやってくる芝居を再現して楽しんだ。中でも『戻り駕籠(かご)』が得意だった」
泉の父は琉球古典音楽をたしなんだ。三線を手にした父の音楽仲間が家に集まる日を心待ちにした。「私を音楽に導いたのは芝居であり、父の三線だった」
平安座小中学校にある数台のオルガンの音色に親しんだ。中学の音楽教諭からピアノを学び、「将来は音楽の道に進む」と意思を固めた。
前原高校では合唱部とバンド部に所属した。男子寮で2年間暮らし、ピアノの練習に没頭した。「本島の生徒に追い付こうと夜中までピアノを弾いた。週末は土曜の夜から朝まで練習した」
泉は東京芸術大学を目指したが米統治下の沖縄では情報は少なく、試験の課題曲すら知らなかった。それでも進学をあきらめきれず、上京。築地市場やオペラ団体で働きながら勉強し、一発で東京芸大声楽科に合格した。
74年、音楽の指導者として琉球大学教育学部に赴任。イタリアやドイツに留学し、西洋音楽を追究した。その一方で沖縄の音楽にも軸足を据える。その一つが宮良長包の作品だった。
「西洋音楽を体験したことで、より沖縄が見えてきた。自分の足元、血の中にも音楽がある」
古希のコンサートでは琉球古典音楽の「伊野波節」を歌った。「私は、父の音楽に回帰したことになる」と泉は語る。
70歳を超えた今も泉は現役の歌手。舞台の企画・演出・出演をこなし、合唱団6団体の指揮者を務める。「働き盛り、全盛期」という気概を込め、泉は「さらばんじテノール」を自称する。
(文中敬称略)
(編集委員・小那覇安剛)
【前原高校】
1945年11月 開校。高江洲初等学校校舎で授業を開始
46年3月 与那城村(現うるま市)西原に移転(現与勝中学校)
58年6月 具志川市(現うるま市)田場の現在地に移転
73年3月 春の甲子園に出場。夏の甲子園にも出場(8月)
5月 若夏国体で女子ソフトボール、男子バレーボールが準優勝
80年 定時制が閉課程
96年 夏の甲子園に2度目の出場