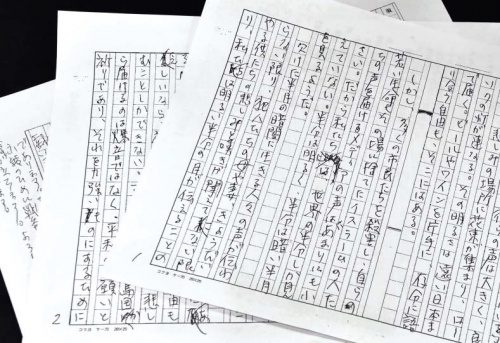
沖縄に思いを寄せた俳優菅原文太さんが他界して1年。妻で辺野古基金の共同代表を務める菅原文子さんが1周忌に当たり、琉球新報に寄稿した。
フランスの悲しみや怒りを世界に届けるメディアは数多くある。彼らの声は大きく、よく響く。悲しみの場所に花束が集まり、ローソクの灯が連なる。その明るさは遠い日本まで届く。ビールやワインを片手に、存分に語り合う自由も、そこにはある。

しかし、多くの市民たちを殺害し、自らの若い生命もその場に捨てたイスラームの人たちの声を届けるメディアの声は、あまりにも小さい。だから私たちには、世界の半分しか見えていない。半分は明るく、半分は暗い半月を見るようだ。
欠けた半月の暗闇に生きる人々の声が伝わらない限り、犯人たちの母や妻、きょうだいや子供たちの悲しみと嘆きが聞こえてこない限り、私たちは明るい半分の月が伝えることのすべてが真実なのかどうか、信じて良いのかを決めることはできない。
半月の暗闇では、パリでそうであったように、倍返しの空爆で殺された人々に花束が積まれているのか、ローソクが惜しみなく燃えているのか、かつて私たちの国の暗い戦争の時代に、妻や母や子が、夫や息子や父の死を悲しみ嘆くことが許されなかったように、半月の片側では今も許されていないのか、有無を言わせず赤紙一枚で戦地に引き立てられていったように、同じように命じられて死んでゆくのか、それらを知ることなしに、安全な場所から明るい半月の片側にだけ花束を捧げることはできない。
そこにも富と自由が、ここと同じようにあるなら裁きのつけようもあるが、富も自由も乏しいなら、私たちはそれを痛み、悲しむことしかできない。アジアの辺境の島国から届けるのは爆音ではなく、平和への願いと祈りであり、それを力強いものにするために戦っている者たちが少しでもいるという希望だけだ。
大国の軍需産業の強欲の前に、世界の理性と叡智(えいち)は声もなく色褪(いろあ)せる。テロに軍事力で臨む時、その爆音の大きさに大義は吹き飛び、憎悪と復讐(ふくしゅう)の灰が地にも心にも積もり続ける。



