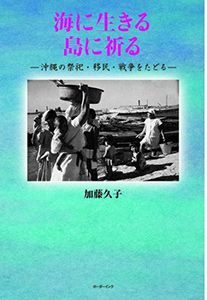
太平洋の大地図を広げてみると、琉球弧の島々はまるで砂礫(されき)のように小さい。そして大洋に点在する無数の島嶼(とうしょ)のひとつだと改めて実感する。地球が水惑星であること、人間にとって海がいかに大きな存在かを教えもする。
この本は、そうした島である沖縄島の糸満と、具志頭(ぐしちゃん)の港川、久米島の奥武(おう)島、宮古の池間島から物語が展開する。
人間が伝統的慣習のなかで家族と共同体を維持しながら個々の生を営むという、じつに平凡だが困難を伴うことが、淡々と語られる。世にいう有名人こそ一人も出ないが、しかしこんな小さな島の、さらに狭いシマの人間でありながら、何と意気が高くて波乱に富んだ人生経験者の多いことか。今更ながら私たちの足元をみせられて驚くのだが、例えば、トラック諸島の「南洋帰り」だという港川の上原キクさんについて記述した箇所など、私は直接ご本人に会って話を伺いたい欲求にかられる。
米軍の空襲でトラックを引き上げたものの、郷里では沖縄戦が待っていた。しかも夫の牛一さんは少年のときにシンガポール方面で漁師をしていて、その後、太平洋戦争でインドの強制収容所に抑留された体験をもつひとであった。さらにもう一例、奥武島の玉城ノブさんと上原秀さん姉妹の、ともに新婚早々の夫を中国戦線で失う過酷な人生が、漁村の家族と庶民の暮らしの地点から開封されていく。
おそらく、現代感覚からすれば、国家間の戦争が、つつましく生きる民衆を途方もない辛苦の淵に陥れたことは、悲劇にしか見えないのだろうが、それを笑って振り返る彼女たちの明るさは、ニライカナイの豊穣(ほうじょう)信仰にも通じるような気がする。
思うに、かくも人間性豊かな人々と幸せな邂逅(かいこう)をした加藤さんだが、では遥(はる)かインドにまで彼らの足跡を追い求めていく行動力と眼差(まなざ)しの根源は何なのか、私はそれをも想像する。
「沖縄に寄り添う」という言葉が、政治だけでなく学者の世界においても安っぽくなった今日だけに、本書の奥にひそむものが光って見えるのである。
(伊佐眞一・沖縄近現代史家)
かとう・ひさこ 1937年生まれ。法政大学沖縄文化研究所国内研究員。1998年から約10年、浦添市の小湾字誌編集委員会による「小湾字誌」(3部編)の編集・執筆に関わる。



