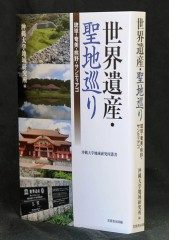
「奄美・琉球」が世界遺産登録を目指し、暫定リストが提出されたことが報道され、話題になったのは今年1月のことであり、その詳細な解説をも盛り込んだ本書は時宜を得た出版である。
本書の内容は(1)世界遺産条約の仕組みと今を知る(2)琉球王国の世界遺産(3)聖地巡りとしての世界遺産(4)新たな世界遺産に向けて-の4章からなるが、世界遺産の意義や保全・活用の方途、進行中の奄美・琉球の世界遺産登録に向けての課題や県民の役割等についても詳述されており、あらためて世界遺産についての理解が深まることになる。
今回の「奄美・琉球」が「自然遺産」として登録されれば、沖縄が文化遺産と自然遺産を持つ国内唯一の地域となる意義深さなどを知ることにもなる。
地域が世界遺産を生かすという視点から、登録後の観光客数の増加等にも言及している。1993年に世界遺産に登録された屋久島では、20年間で入り込み客数が2倍、宿泊施設数は3倍に増え、ガイドが150人を超え、大きな産業に成長しているなどの例も挙げられているが、あくまでも持続可能な利用であるべきことを指摘する。(世界遺産登録に不可欠な要件として(1)顕著な普遍的価値の証明(2)真正性及び/または完全性の条件を満たすこと、に加えて(3)保護を担保する万全の保護措置が整っていることが挙げられ、「持続可能な利用」というのが条件の一つとなっている)。
すなわち、地域の個性の輝きは、観光地としての魅力を増し、経済的な豊かさにもつながるものであるが、地域の個性やその暮らしを豊かにする資源を失わないようにとの警告も忘れない。そのためには、世界遺産を守り、生かすための仕組みづくりが重要となる。
本書は、沖縄大学地域研究所が取り組んできた市民講座、テキスト刊行、検定実施等々世界遺産や環境問題等一連の普及啓発活動の成果の一つとも言えよう。「世界遺産を守り、活用して、地域の持続的発展ツールとするにはどうすればよいのか」を考えるいい契機を与えてくれるものだと思う。
(琉球大学名誉教授・平敷徹男)
売り上げランキング: 1,145,829




