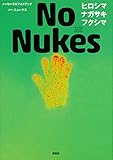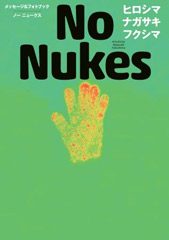
エンタメが世の中を面白くする理由
忌野清志郎が亡くなって6年が過ぎたこの5月、テレビで何本か特番が放送された。曲作りの秘密に迫るドキュメンタリーや、名曲『トランジスタ・ラジオ』のタイトルをつけた青春ドラマなどは、病に倒れたアーティストの追憶に浸るにはいい内容だと思う。
それでも、やはり一番胸に迫ったのは、闘病から復帰して再びファンの前で歌ったライブ番組。今、テレビを見ている私たちはその後の運命を知っている。このときの清志郎の心中はどうだったのかと想像するとつらくなるが、唯一無二のエンターテイナーと長く付き合うつもりなら、あれこれ考えるよりも、思い切り楽しむ方がいい。エンタメの力はそこにある。楽しめば元気になれる。
この放送の少し前に1冊の新刊書が出た。その中に、清志郎が歌った反原発ソング『サマータイム・ブルース』の歌詞が収録されている。なぜかというと、この本は『No Nukes(ノーニュークス)』(講談社刊、1620円)というタイトルで、「兵器と電力から核を排除するための役に立ちたい」という思いで編集されているからだ。清志郎だけでなく、坂本龍一、吉永小百合、渡辺謙、美輪明宏、井上ひさし、重松清といった人たちや、広島、長崎、福島の大学生ら20人以上の文章と詩が載っている。被爆体験や反核の理論についての真剣で誠実な文章が並んでいて、「原爆と原発の接点」の知識も得られる。見開きのカラー写真も多く、原爆ドーム前での灯籠流し、住民が避難して犬が取り残された福島県双葉町の風景、原発の原子炉圧力容器、千葉で開催された反核フェスの会場など、ぱらぱらと見ていくと、どこかのページで手が止まるだろう。
その中で、清志郎の『サマータイム・ブルース』は異彩を放っている。一見するとふざけているような歌詞。清志郎が歌うのはこんな光景だ。あくせく働いて、休みに出かけてみると、日本の海岸のあちこちに原発が建っている―。地震だって起こりそうなのに、誰のため? 分かんねえ、欲しくねえと歌は続く。深刻な問題のはずだが、ロックの名曲をカバーしたギターのシンプルな演奏は終始軽快なリズムを刻んでいる。日本の原子力政策をからかい、抗議する曲。しかもCDがリリースされようとした1988年夏、直前に発売が中止され、別のレコード会社から売り出される騒動があった。久しぶりに『No Nukes』で見つけ、歌詞を目で追っているだけで、あの声、あの演奏がよみがえってくる。いわゆる「反○○ソング」はいろいろあるが、この曲は世に出た時から、いや出る前から世間の注目を集め、その後も長く多くの人の記憶に残る希有な反原発ソングになった。
音楽にはこんなこともできるのだと、あらためて思う。ブラックユーモアが効いていて、思わず笑い、楽しんだ後で原発は本当に必要かと考える。原子力なんて興味がなかった人たちも振り向かせたに違いない。
難しいことを言わなくても、笑いや楽しさの中に真の問題を織り込むのはかなり高度なワザだが、古くから多くの表現者が挑んできた。知識や情報を広げることとは別の次元で、自由な表現は私たちにとって極めて大切なことだ。その鋭さに気付いたからこそ、CDの発売を中止しようとする人たちがいたのだろう。曲を世の中に届けることで生きていくアーティストにとっては、まさに命がけの表現だったとも言える。こんな理屈はともかく、清志郎の『サマータイム・ブルース』は今も生き続けている。
残念なことに、私たちはこの曲のリリースから23年後、深刻な原発事故を体験する。2009年に亡くなった清志郎は、こんな事態を見ることはなかった。今、聞き直しても曲の発表当時のような笑い方をすることはもうできない。だが、直面する現実の中で『サマータイム・ブルース』の重みは増している気がする。困難ではあっても、元気をなくしてはいけないと思い直す。息苦しい時代の中に吹き抜ける風として、アーティストの表現の自由は私たちを励ますものでもある。清志郎の出番はまだ多いだろう。
思ったことを自由に言える社会が貴重であることを、最も分かりやすく、最も遠くまで伝えるのは表現の力だろう。もちろん、どんなものでもいいわけではない。つまらなければ空回りして消えていく。今だからこそ、磨かれたエンターテインメントの活気がほしい。人々が元気になれば世の中が面白くなる。(杉本新・共同通信記者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
杉本新のプロフィル
すぎもと・あらた 1963年生まれ。文化部に在籍。趣味で聴くときはつい若いころと同じ音楽を選んでしまい、いまだに70年代、80年代。耳は保守的なものだと実感。
(共同通信)
売り上げランキング: 4,877