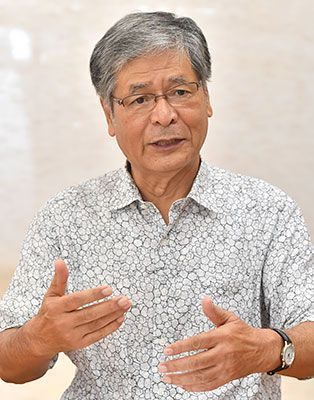
米軍普天間飛行場に組み敷かれた先祖伝来の土地を返還させ、佐喜眞道夫さん(74)が佐喜眞美術館を開いてから26年近くになる。東京で鍼灸師をしていたころ、画家の故丸木位里、俊さん夫妻に出会い、1984年に完成した「沖縄戦の図」に感銘を受けた。この作品を沖縄で常設展示したい―と決意して10年、粘り腰の交渉で開館にこぎ着けた。
「戦争の悲惨さの本質は地上戦にある。住民が犠牲になった沖縄戦の惨劇を二度と繰り返してはならない」と語る。「もの想(おも)う空間」を掲げ、芸術を通し、沖縄戦継承と不戦を訴えてきた。
ケーテ・コルビッツら平和にこだわる作品を収蔵する。修学旅行生らに自ら講話し、戦争と平和を学べる美術館として定着し、来館者は100万人を超えた。「新型コロナウイルス禍の今こそ、多くの県民に足を運んでもらい、平和を希求する作品と対面してほしい」と呼び掛けている。
「もの想う空間」を戦争なき未来の礎に

―昨年10月、入館者が100万人を超えた。「沖縄戦の図」を鑑賞しながら、基地の島・沖縄の現実を学べる美術館の存在感が増している。
「丸木位里、俊さん夫妻の『沖縄戦の図』は世界中、国内170カ所で巡回展覧された。日本人の戦争体験の多くは海外の戦場で、あとは米軍の空襲だが、住民が犠牲になる地上戦に戦争の悲惨さの本質がある。沖縄戦を体験した沖縄のことを学び、丸木夫妻は作品を描いた。沖縄戦と今の米軍基地の過重負担は地続きで、将来の戦争にもつながりかねないという感覚を美術館から伝えることができたなら、そこは大変良かった」
丸木夫妻の「沖縄戦の図」 自殺思いとどまった生徒も
―修学旅行生の来館者が多い。「沖縄戦の図」と館長の講話に影響を受ける若者たちが多くいる。
「人生で最も多感な時期に来てくれた彼らが大学生になったり、結婚したりした後、あるいは教師になって生徒を連れて来館してくれる。うれしいことだ。人生に絶望していた17歳の少女が『生きる意欲を与えてくれた』と自殺を思いとどまったこともある。凄惨(せいさん)な戦争を二度と起こさず、沖縄に住む子や孫を絶対に巻き込んではいけない―という沖縄戦体験者の思いが丸木さんの作品に落とし込まれ、美術館に託された。若者たちはメッセージを感じ取る。あの少女の感想文を読んで、美術館を造って良かったと強く思った」
米軍は開館快諾、邪魔したのは日本政府側
―1994年の開館までの経緯、苦労を振り返ってほしい。
「建設場所探しに難渋していたころ、基地内にあった先祖伝来の所有地を訪ねた。門中墓を見た時、『お前、ここでやれよ』という天の声が聞こえた気がした。沖縄戦で失われたはずの緑陰が残り、普天間基地の向こうに海が見える。設計を頼んだ建築家の真喜志好一さんが示した『沖縄戦の図』を置く場の条件((1)心を癒やす緑陰がある(2)沖縄の心と祈りを伝える御嶽や亀甲墓に近い(3)屋上から海が見える(4)広さは500~600坪)にピタリと合った。土地を返還させ、ここに造ると決めた」
―国側は強い難色を示した。
「那覇防衛施設局に直談判したが、対応した本土出身の課長は沖縄をなめていた。『土地を返してほしい』という言葉以前に、私という人間に驚き、目の前で『我々が制圧した沖縄にこんな人がいるはずがない』と部下の係長に言い放った。戦略を改めてソフトに要請しようと、次からスーツにネクタイ姿で訪ねたが、担当部署の30~50人の職員は敵意むき出しの視線を向けてきた。施設局はほとんど動いてくれなかった。当時の桃原正賢宜野湾市長に後押ししてもらい、後に市長になる比嘉盛光さんが、在沖米海兵隊の不動産管理事務所長で沖縄系のポール・ギノザ所長に引き合わせてくれた。ポールさんは『美術館ができると宜野湾市は良くなる。問題はない』と返答してくれ、返還の門戸が開いた。邪魔していたのは日本政府側だった」

―「もの想(おも)う空間」を掲げてきた。
「小さな島だが、沖縄の先達は物事を深く考える力を発揮し、さまざまな苦難を乗り越えてきた。文化、芸術を通して沖縄に横たわる不条理を克服し、沖縄の内にある怒りのマグマをみんなで共有してかみしめる場にしたい。一貫して、美術館をそうした深く考える場にしたいと考え、活動してきた」
―沖縄戦75年の節目の年に、あらためて「沖縄戦の図」を展示し続けてきた意義を聞きたい。
「数え切れない沖縄戦体験者の証言を聞き、丸木夫妻が制作した。壮絶な地上戦の体験を思想、哲学の領域に深めた。普遍化して戦争のない未来の社会をつくるための文化財、礎のような存在にしていきたい」
―熊本での幼少期、東京での大学時代にウチナーンチュへの差別を実体験された。佐喜眞さんが本土からの来館者に話す言葉の奥行きにその体験が反映されているのではないか。
「小学校で『琉球猿』とはやし立てられた。大学時代には、沖縄出身者の姓と分かった途端、私を見下し、突然『おい、お前』と高圧的になる初対面の青年がいた。沖縄の人間としての自意識とヤマトンチュの沖縄に対する偏見との溝の深さにおののいた自分がいた。沖縄にこだわることは社会と日本、人間を考えることでもあり、沖縄という回路を通して世界、日本の侵略戦争で被害を受けたアジアを見ている気がした。沖縄に基地を押し付けながら、見て見ぬふりをする本土側の視線を俯瞰(ふかん)して分析し、共感を呼び起こす語り口になっている面があるかもしれない」
―沖縄は、日本の民主主義が機能しているかを問うとげのような存在だ。佐喜眞さんの目にはどう映るか。
「民主主義を踏みにじる権力の姿は将来の戦争につながる。辺野古新基地(建設海域の軟弱地盤改良)に兆単位になる税金をつぎ込む愚かさに国民が気付かねばならない」
新型コロナ禍の戦後75年 平和希求の作品と対面を

―新型コロナ禍の影響はどうか。
「2001年の9・11同時多発テロ後、修学旅行生が半分以下に減ったのと比べても、感染症の影響は甚大だ。今年の入館者は前年の半減以下の2万人以下になるだろう。一方で、あらためて戦争を深く考えたいというお年寄りの来館者が増えている。8月は県民の入館料は無料。コロナ禍のこういう時期だからこそ、多くの県民、特に若者に沖縄の一番大事な、平和を希求する哲学を理解できる作品と対面してほしい」
―ご両親の教育は、佐喜眞さんの人格、美術館運営に影響しているか。
「疎開先の熊本で医師をしていた父は毎日100人を診察し、夜は10~15件も往診していた。働き詰めの父、母に随行し、絶対に戦争をしてはならないということ、美しい沖縄の原風景の話をたくさん聞いた。いとこやきょうだいから『美術館はお父さんが一番やりたかったすてきな仕事だ』と言われる。生活に余裕があれば、少しずつ他の人に尽くせと言われたことも美術館の運営、私の生き方に息づいていると思う」
(聞き手・編集局長 松元剛)
さきま・みちお
1946年、家族で疎開していた熊本県甲佐町で生まれる。高校卒業まで熊本で過ごす。74年、立正大学大学院(史学研究科)修了。75年、絵のコレクションを始める。79年に千葉と東京で鍼灸院を開業。83年、丸木位里、俊夫妻と出会い、不戦の思いを込めた夫妻の「沖縄戦の図」を展示しようと、94年に宜野湾市上原に佐喜眞美術館を開館。95年、国連出版の『世界の平和博物館』に収録される。2010年、琉球新報活動賞を受賞。18年、同美術館が自由都市・堺「平和貢献賞」を受賞。
取材を終えて
本質突く不戦への思い

柔和な笑みを絶やさない佐喜眞さんの本質を鋭く突く語り口は穏やかだが、人を引き付ける。私が沖縄を訪れる本土の報道関係者らに「ぜひ訪ねて」と薦める場が佐喜眞美術館である。二度と愚かな戦争は起こさせないという館長の決意を肌で感じ、話を聞いた人は、沖縄に米軍基地の負担を偏在させる本土の側の立ち居振る舞いに思いが至り、胸にさざ波が立つはずだ。
2013年夏、琉球新報が招いた映画監督のオリバー・ストーン氏に随行した。原爆忌の広島、長崎の後に来沖した巨匠は疲れ切っていたが、佐喜眞美術館で「沖縄戦の図」を目にした途端、背筋がピンと伸びた。「とても力強い絵だ」と目を輝かせ、佐喜眞さんの「集団自決」(強制集団死)の解説にも聞き入っていた。不戦にこだわる作品群を収集する国際性豊かな眼力も発信力の源泉だろう。
(編集局長・松元剛)
(琉球新報 2020年8月11日掲載)



