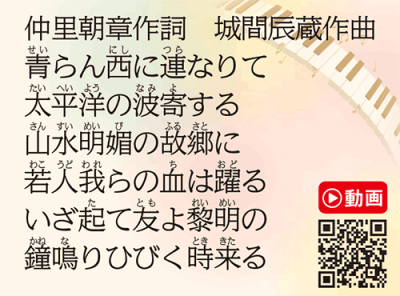1964年9月8日。東京オリンピック聖火リレーの走者として沖縄本島北部の東海岸を駆ける2人の宜野座高校生がいた。21期で、那覇空港ビルディング社長の安里昌利(73)と、22期で小説家・詩人の大城貞俊(72)である。
2人は同時期に宜野座高校で学んだ。安里は柔道部に所属し、コンセット(米軍のかまぼこ型兵舎)の練習場で汗を流した。大城はテニスの選手として活躍した。琉球大学に進学した2人は激化する学生運動に直面した。
卒業後、安里は経済界へ進んだ。沖縄銀行頭取や会長、沖縄県経営者協会会長を歴任し、県経済界の発展に尽くした。県立高校教師となった大城は小説や詩の世界で活動し、県内外の文学賞を受賞。旺盛な創作・評論活動を続けている。
57年前、やんばる路を走った2人は今も、それぞれのフィールドを駆けている。

那覇空港ビルディング社長の安里昌利(73)は1948年、宜野座村松田で生まれた。いわゆる「団塊の世代」に当たる。戦前、ブラジル開拓を経験した父は村内で手広く農業を営んでいた。63年に宜野座高校に入学。放課後は毎日畑に通い、父を支えた。
「真面目な生徒だったと思う。父を手伝うのは当たり前。どこかに遊びに行くということもなかった。夏休みも畑作業。休みは1日もなかった」

東京オリンピック聖火リレーで宜野座村内を走った。「正走者をバスケット部のキャプテンが務め、われわれ伴走者は予備のトーチを持って走った。誇りでしたね」
高校時代から「経済に漠然と関心を持っていた」という安里は67年、琉球大学経済学科に進む。学生運動が高揚期に向かい、セクト間の対立が激化していった。
3年になった安里は大学が封鎖されたのをきっかけにアルバイトをしながらソ連や北欧、中近東の国々を回る放浪の旅に出た。帰郷したのは1年後だった。
73年に沖縄銀行に入行。外国為替を担当した。銀行マンとして「海洋博ショック」と呼ばれた深刻な不況を経験する。2002年、頭取に就任。12年から18年まで沖縄県経営者協会の会長を務めた。
同じクラスだった仲間や教師との親交が続いている。「今も集まれば、きょうだいのような感じだ。人と人との絆をつくった3年間だった」と安里は語る。

小説家で詩人の大城貞俊(72)は聖火リレーで久志村(現名護市)内を走った。「トーチから上がる煙のにおいをかぎながら走った」
1949年、大宜味村大兼久で生まれた。教員の父の転勤に伴い、国頭村楚洲や久志村三原で暮らした。64年、宜野座高校に入学した。
宜野座高校は米軍基地が広がる金武と辺野古に挟まれた地にある。「『基地の街』から通ってくる同級生は大人びて見え、こっちは萎縮してしまった」と語る。「自分を見失い、生きる指針を見いだせずにいた」という大城は次第に文学に傾倒していく。
69年、琉球大学国語国文科に入学した。学生運動が熱を帯びていた。「政治の嵐の前で葛藤した。傍観者でいいのか、コミットすべきなのか、とても迷った」
「政治の嵐」の中でドロップアウトする者、自ら命を絶つ者もいた。大城も思い詰め、後ろめたさを感じながら大学を卒業。高校教師の道を歩み、創作活動を続けた。転機となったのが父の死だった。「病気と闘う姿を見て、父の一生を考えるようになった」
父の人生、そして沖縄の家族を見つめる中で大城は父の赴任地であり、幼かった自身が育った国頭村楚洲を舞台とした小説「椎の川」(92年)を書いた。
その後も沖縄の家族を描くなかで大城は沖縄戦体験と向き合う。「家族や命をテーマにすると沖縄戦とぶつかる」。故郷である大宜味村大兼久で集めた証言を基に2016年、「奪われた物語―大兼久の戦争犠牲者たち」をまとめた。
「僕の転換点になった」と大城は語る。
(文中敬称略)
(編集委員・小那覇安剛)
【宜野座高校】
1946年2月 祖慶、福山、古知屋、中川、久志、大浦崎の各校を統合し、現在地に宜野座高等学校として創立
48年4月 6・3・3制実施、新制高校として出発
60年4月 琉球政府立宜野座高校に移行
72年5月 日本復帰により県立高校に移行
2001年3月 21世紀枠で春の甲子園に出場、ベスト4。8月、夏の甲子園に出場
03年3月 春の甲子園出場