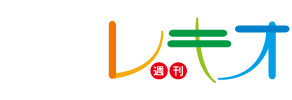地域に根差した小さなあめ工場

一粒口に入れた瞬間、素朴でやさしい甘さが口いっぱいに広がる……。「黒糖飴」「シークヮーサー飴」など、沖縄の素材にこだわった商品を製造している沖縄市の「竹製菓」。沖縄ではおなじみの小さなあめメーカーだ。祖父と父の後を継ぎ、現在代表を務めるのは3代目の竹元史郎さん。昔ながらの製法を守り、沖縄ならではのあめ作りに励んでいる。
沖縄市宮里の住宅街にたたずむ「竹製菓」。甘い香りが漂う工場内では、釜の中で加熱された液体がさまざまな工程を経て光沢のあるあめ玉に変わっていく。
竹製菓は創業90年目の老舗あめ店。現代表の竹元史郎さん(46)は3代目で、25年前に家業を継いだ。以前は300社近くあった県内のあめ製造業者は、竹製菓を含めて現在数件だけ。家族と従業員の合計8人で、昔から県民に親しまれてきた味を守り続けている。
竹製菓の歴史は1931年までさかのぼる。元史郎さんの祖父、玉光さんが出身地の鹿児島県沖永良部島で創業。当時はカステラやせんべい、あめなどを製造していた。1958年に宜野湾市に移転。元史郎さんの父・元三郎さんが2代目になった後、1973年に現在の沖縄市宮里に移り、あめ一本に製造を絞り込んだ。「賞味期限も長く、形の悪いあめも溶かせば再利用できる。無駄のないのはあめ玉だけだった」と元史郎さんはその理由を語る。
県産素材で商品作り
原料にこだわり、ほぼすべて県産素材を使用。1974年から製造されている「黒糖飴(あめ)」の他、タンカン果汁入りの「たんかんのど飴」など、現在約30製品を製造。伝統の味を守り続ける一方、与那国島産の長命草を使った「長命草のど飴」や泡盛を使った「残波 ザンシロ飴」など、新たな商品も開発し、県内外で好評だ。自社製品の他、他社ブランドの製品を受託製造する「OEM」商品やオリジナル商品のリクエストにも対応している。これまでに作った製品は100種類を超えるという。

工場では早朝からあめの製造が始まる。砂糖と水あめを145度ぐらいまでぐつぐつと煮詰めた後に、冷却板に流し込む。香料などの原料や割れてしまったり、形が悪くなってしまったりしたあめも生地に混ぜて溶かし、手作業でこねていく。あめ生地は20㌔あり、かなりの力仕事だ。この日は元史郎さんの息子で半年前から修行を始めた隆一郎さん(20)が行っていた。

手作業で味を付けた後は、機械に通して、あめ玉の形を形成し、検品、包装していく。一日最多で600㌔は作れるという。あめ玉1個5グラムだから、12万個のあめ玉を作ることができる計算だ。


あめで地域を応援したい
手作業と機械を併用している竹製菓。「県内で量販店に対応ができる生産量を確保できる工場はうちだけ。機械を導入することによって生き残ることができた」と元史郎さんは話す。それでも味を決める作業は今も手作りを大切にしている。「手作りであるがために人件費もかかり、コスト的には全て機械化で大量生産できる大企業と比べ高くなる。でも、大量に作れない分、オリジナル商品などにも柔軟に対応できる」という強みがある。

「今後も沖縄の特産品をあめ玉にして伝えていきたい。地元の素材のPRになるきっかけになるような、小さな製造会社であり続けたい」と元史郎さんは意気込む。あめ玉とともに沖縄の味をこれからも届け続ける。
(坂本永通子)

竹製菓
住所:沖縄市宮里3-21−35 (マップはこちら)
電話:098-989-1937
(2021年4月8日付 週刊レキオ掲載)