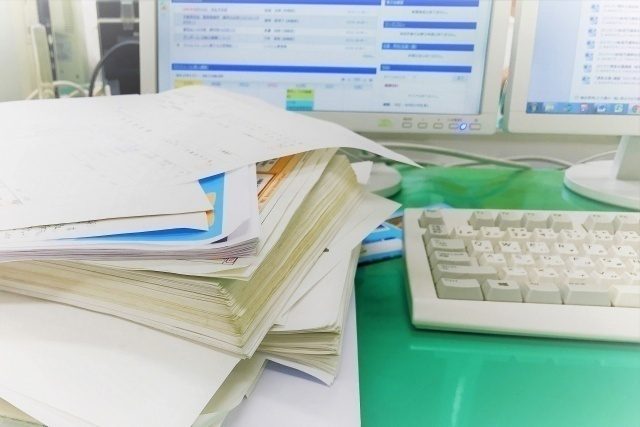
業務改善のススメ
新年 明けましておめでとうございます。
2019年を迎え、新たな事業展開や計画などを立てられたという企業もあるのではないでしょうか。
「平成」も残りわずか。新たな時代に突入し、少子高齢化に伴う労働人口の減少やAIの進化など、私たちを取り巻く環境は今後ますます変化していくことが予想されます。だからこそ今、ご提案したいことがあります。
それは「業務の棚卸し」です。

◇執筆者プロフィル
波上こずみ(なみのうえ・こずみ) コズミックコンサルティング代表
子育て・介護と仕事との両立に苦しんだ経験を踏まえ、2016年に起業。「働く人のモチベーションを組織の活力へ!」をテーマに、沖縄の企業や個人を対象としたコンサルティングを手掛けている。1976年、那覇市首里生まれ。1男1女の2児の育児中。
「忙しい」は本当?
「現場が忙しいのに、人も採用できない。さらに人も定着しない。どうすればよいのでしょうか」
最近こういうお問い合わせが急増しています。
少子高齢化により、圧倒的に労働力は減少しているのは明白です。さらにITツールの進化や顧客ニーズの多様化など、変化のスピードが急激な現代において、以前までは必要のなかった業務が新たに増えているのも事実だと思います。
ですが、あえて提起します。
「忙しい」って本当でしょうか。
一つの事例をご紹介します。
人材定着をテーマに、沖縄県内のある保育園でコンサルティングを実施した時の話です。
こちらの保育園も例に漏れず、「忙しくて人が足りない。保育士を採用したいが募集をしてもなかなか応募がない。そんな中、メンタル不調により休職者も出て、立ち行かなくなりつつあるんです」という課題を抱えていました。
園長や主任、現場の先生方に聞いても異口同音で「忙しい」との声が飛び交っていました。
「具体的に何が忙しいのでしょうか」と聞いてみると、
「とにかくやらなきゃいけないことがたくさんあって忙しい」という反応。
そこで業務量や業務内容について検証をするために、全職員対象に1週間ごとの業務予定と実際に行った業務内容について記録を取ってもらい、チームメンバーに共有するというアクションプランを実施しました。このアクションを約3カ月間続けてもらい、その記録をそれぞれのチームメンバーで分析してもらいました。
すると驚いたことに、一人一人それぞれ自分の仕事のやり方を軸に動いていて、チーム内で類似する業務をお互い知らずに行なっていたり、「この仕事はあの人しかできない」と思い込んでいる業務が、実はほかのチームではみんなで行なっていたり・・・と業務のムラや無駄があることが浮き彫りになったのです。
つまり、チームによって業務の取り組みに差が生じていたり、さらにチーム内での情報共有も行われていなかったり、といった現状が分かったのです。
- ここまでやるのは当然
- この仕事はこうすべきだろう
- この仕事は何でやるのかよくわからないが、今までやってきたから必要なんだろう
こういう思い込みの中、一人一人の仕事のやり方に依存していて「チームで動く」「園全体で動く」という意識が希薄になっていたのです。これは「自分たちの業務を可視化してみる」というアクションを起こすまでは、本人たちも無意識のうちにやっていたことでした。
この結果には経営陣よりも、むしろ保育士さんたちの驚きと気づきが大きく、「なんで今までみんなで共有しなかったんだろう」という素直な感想まで出てくるほどでした。
この気づきにより、今まで「1人で一つの業務」という考え方だったのが、「2~3人で複数の業務をやる」という体制に変え、積極的に業務の共有化を図る動きがとられました。
このことにより何が起こったのか。
まず全体の勤務時間がギュッと短縮され、超過勤務が格段に減少しました。加えて、保育士の先生から「以前と比べてすごく働きやすくなった」という声が複数上がり、何と今まで応募がなかった人材獲得も一気に2名もの採用に繋がるという現象が起きたのです。
業務を見直してみる → 無駄が排除でき本当に大事な仕事を優先的にできるようになる → 仕事が楽しくなる→ 働いている人が生き生きする → 人材が定着する → 人が採用できる
そんな好循環が生まれ始めたのです。
忙しい。
その一言を発しようとするその前に、一度立ち止まってみましょう。
「本当に全部必要な業務?」
「本当に今のやり方でいい?」
こうした問いを社内で投げかけて、今の業務を見直してみませんか。
スクラップの次はビルド!
ここまでの話を振り返ると、「業務の断捨離こそ善」という考え方になりがちですが、それは違います。前述した通り、時代の変化に応じて、以前はなかった業務が今後ますます新たに出てくるからです。
スクラップの次は、ビルドです。
ただし、ここで強調したいのはビルドの組み立て方です。
突発的に起こったことに対して、その都度慌てて対応する「対処療法的なビルド」ではなく、
世の中で起こっていること、クライアントや地域の人々の流れ、消費者の傾向など、経営者だけではなくスタッフ一人一人がさまざまなシーンでアンテナを立てて、一歩先を読んで取り組みを計画する「建設的なビルド」が必要なのです。
- 今 お客様や地域の人々が求めていることは何か
- 今後こんなサービスや製品が人々を助けるのではないか
- 新しいものを生み出すための仕事のやり方は今までとは異なる工夫が必要ではないか
こういう視点で、日頃から社内マルチコミュニケーションを土台に、気づきやアイディアを共有できることがポイントです。
※参考記事はコチラ→人手不足なのに社員がまた辞めた!? そんな職場に見直してほしいこと【働き方改革@沖縄(3)】
https://ryukyushimpo.jp/style/article/entry-828167.html
「対処療法的なビルド」VS.「建設的なビルド」
対処療法的なビルドがはびこっている組織においては、何か提案した人がその業務を負わされるという「言ったもん負け現象」が起こっているため、せっかく良い気づきやアイデアを思いついても敢えて言わないという残念な状況になっています。こうした組織では既存業務のスクラップが不十分である上に、突発事項の対応に追われているため、新しいことにチャレンジする余裕がないのです。
一方、建設的なビルドが実現できている組織は「まずは言ってみよう!」という空気感が出来上がっています。「チームで動く」組織なら、「言ったもん負け現象」が起きないからです。小さなことでもスタッフのアイデアや気づきが言える環境こそが、イノベーションを生み出し、ひいては企業成長に繋がるのです。
あなたの企業では、アイデアや気づきを言える環境が整っていますか。
業務改善のススメのまとめ
働き方改革関連法案の成立により、平成31年(2019年)4月1日から、年10日の有給を得ている労働者に対して会社は、5日は有給休暇を取得させることが労働基準法上の義務となります。
「そんなの無理」と言って目を背けている時間はありません。業務改善のためのいい契機と捉えて、動いてみましょう。
「忙しい」というセリフが社内に飛び交う状況であれば、まずは現状をチームや社内で共有してみましょう。「見える化」するだけでも、業務の効率化や削減に繋がります。何の業務を減らすかというのは、その後です。
そして、削減するだけではなく、新たに必要なこと、改良すべきことなど、スタッフ間で定期的に言える場づくりをしましょう。そのためには、社員一人一人がただ単に業務をこなすのではなく、日頃からアンテナを立てて感性を磨くことも大切なポイントです。
「忙しさ」を理由に業務改善を理想論として、何もアクションを起こさず衰退する組織になるのか。
「まずはやってみよう」という姿勢で、「業務の見える化」と「アイデアが出せる場づくり」を進めて成長する組織になるのか。
今こそ真剣に、業務改善に取り組んでみませんか。

執筆者プロフィル 波上こずみ(なみのうえ・こずみ)コズミックコンサルティング代表
1976年 那覇市首里生まれ。沖縄県立首里高校、東京経済大学卒業後、2001年JTBワールド(東京)に入社。04年に帰沖し沖縄観光コンベンションビューローに入職。05年に結婚、08年に長男、11年に長女を出産。復職後、同ビューロー初の組織内人事担当者として、人材育成プログラムを構築、講師を務めた。父親の介護問題にも直面し16年に退職。自身の経験を生かし同年4月、組織コンサルタントとして起業した。
波上こずみ公式HP http://kozumi-naminoue.com/



