
1945年4月3日。米軍が中城村に進攻すると、当時8歳の新垣清徳さん(86)=同村=が避難していた壕の上空に操縦士の顔が見えるほど低空飛行の米軍機が現れ、次々に爆弾を落とした。両親ときょうだい、祖母、いとこ家族の計13人は奥行き5メートルほどの壕の奥で身を寄せ合い、「死ぬならみんな一緒に」と震えながら祈った。
砲爆撃がやんだのは4月半ばだった。米軍が中城を制圧し、戦線は早くも南に移っていた。戦況を知るよしもない清徳さんは不気味な静けさに戸惑った。「戦は終わったのか?」。壕の入り口で祖母の頭のシラミ取りをしていると、サトウキビ畑の向こうから聞き慣れない声が聞こえてきた。「アメリカードーヒャ!」。米兵が迫っていた。足がすくみ、転がるように壕に逃げ込んだ。米兵は何度か「デテコーイ」と投降を促したが、その日はすぐに立ち去った。
両親は「自分たちはどうなってもいいが、子どもたちは…」と泣いていた。緊迫する中、隣の壕にいた同郷の女性が訪ねてきた。女性には3、4歳の子がいて、時折歌声が漏れ聞こえていた。女性は「刃物を借してほしい」と小さな声で頼んだが、母は「死ぬつもりだね」と察し、断った。清徳さんは女性の心情が理解できるという。「あの頃はうんと洗脳されていて、米兵は鬼だと信じて誰もが死を覚悟していた」。
恐怖のどん底にいた清徳さんらの命を救ったのは、「満州オジー」と呼ばれていた親戚のおじいさんだった。たばこを求めて壕を一人で飛び出し、先に保護されていた。米兵と壕を回り、「ンジティクーヨー(出ておいで)、アメリカさんは何もしないよ」と住民に呼び掛けていた。
オジーの落ち着いた様子に、「殺されないのでは」と一筋の望みを見いだして壕から出ると、畑には近隣の壕に避難していた大勢の住民が銃を構えた米兵に取り囲まれていた。皆、無表情で押し黙っており、「いつ殺されるのか」という恐怖感に包まれていた。住民の中に刃物を借りに来た女性の姿もあった。
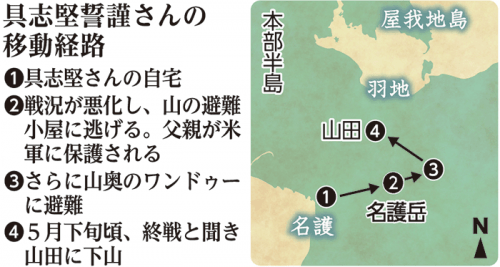
泡瀬の収容所に運ばれ、知人たちと再会してようやく「生きたんだ」と喜びが湧き上がった。皆がわれに返る中、刃物の女性が「アイエーナー! ワンネーチャースガヤ!(私はどうしたらいいんだ)」と取り乱し、大声で泣き出した。おぶった子どもは上半身は着物にくるまれ、足だけがぶらりと出た状態で身動き一つしなかった。「死んでいた。一緒に死ぬつもりが死にきれなかったんだ」。子どもの亡きがらは清徳さんの父らが海岸に埋葬した。
戦後、子を手にかけた女性は人前に出ることを避け、「責めを負うように」ひっそりと暮らしていたという。地域には戦争で大切な人を失い心身に傷を負った人が数多く存在し、長らく沖縄戦について語ることは「タブー」だった。
しかし、戦争体験者が年々いなくなる中で「今なら話すことができる」と、清徳さんは重い口を開いた。「状況が少し違えば死んだのは私だったかもしれない。紙一重だ。僕は生かされているので、戦争の実相を語り継ぐことが使命だと思う」。言葉を選びながら、かみしめるように話した。
(赤嶺玲子)



