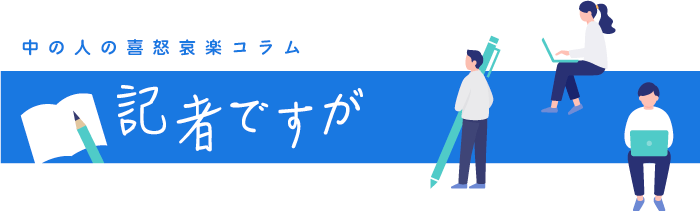
渡嘉敷村で「集団自決」(強制集団死)の生存者を取材した。当時6歳だった女性は、断片的な記憶と母から聞いた話を基に、体験を振り返ってくれた。
軍命を受け、大雨の中を「集団自決」の現場まで歩いたこと。途中、気絶した女性を見て親戚が「どうせ死ぬ。ここに寝かせておけ」と言ったが、母は従わなかったこと。女性が「絶対死にたくない」と泣き、家族で「集団自決」の現場を離れて助かったこと。
親戚の言葉は、待ち受ける悲劇への覚悟が伺える。記憶が断片的なのは、むごたらしい情景を脳裏から消したいと願った少女の本能だろうか。
40代を迎えると同時に、縁あって沖縄に住み、琉球新報で働き始めた私は、取材を通じ沖縄のことを学んできた。同じ琉球弧で「兄弟島」とも呼ばれる古里の奄美と似ている点も多いが、大きく異なる点もある。
「軍隊は住民を守らない」という教訓がそれだ。沖縄では戦争を知らない世代にも、体験者の言葉を通じて浸透している。地上戦を免れた奄美の住民にその感覚は薄く、私自身も沖縄の人々を取材するようになって、体験の重みを実感した。感覚の違いは、国が南西諸島で進める陸自配備に反対する声が広がりを持つか否かという住民反応の違いにも表れているように思う。沖縄に米軍が駐留し続けていることによる基地被害の影響も大きいだろう。
取材を通して気付きを得るきっかけをくれた縁に感謝し、現場に立ちたい。






