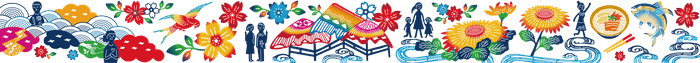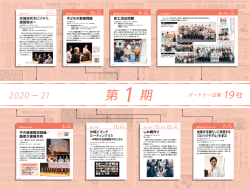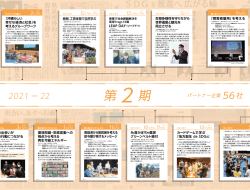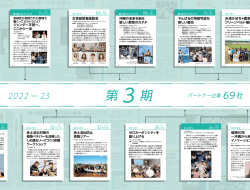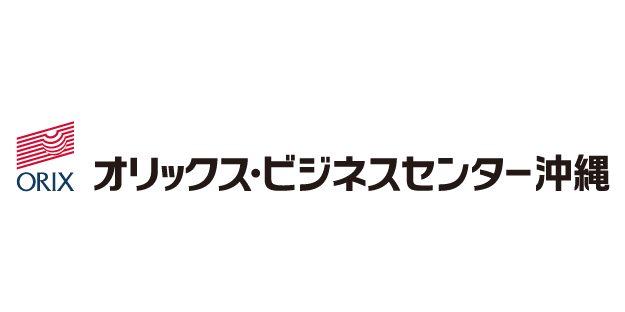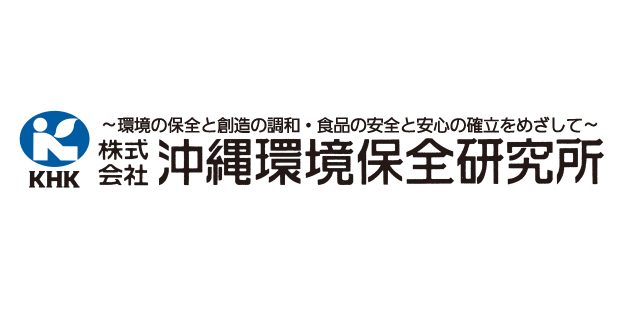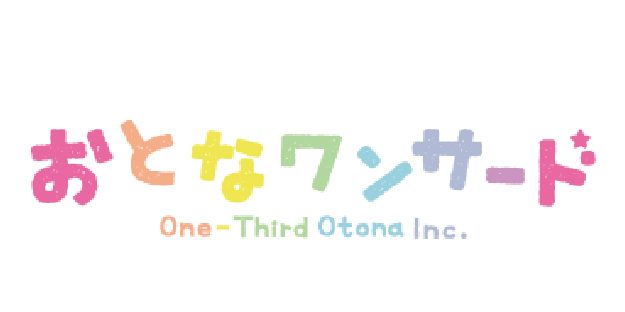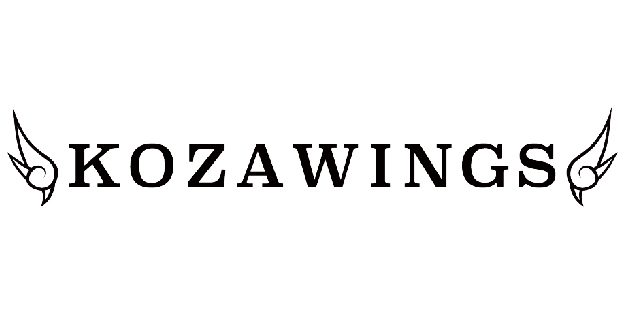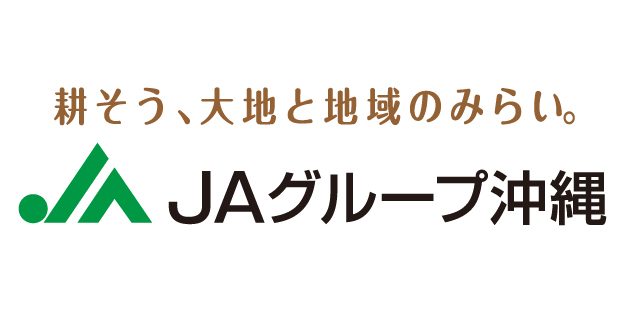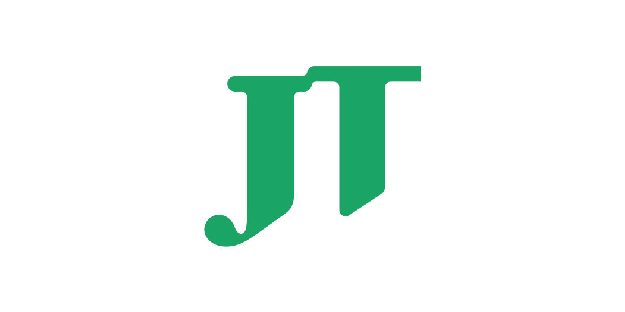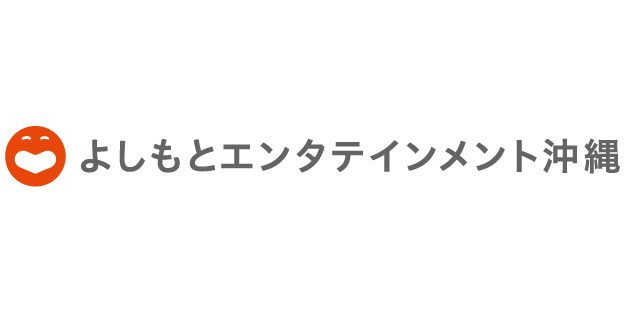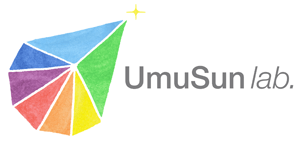「OKINAWA SDGs プロジェクト」は、SDGsに取り組む企業や団体のプラットフォームです。プロジェクトの柱は「つなぐ」「伝える」。世界を変える一歩を、沖縄から。私たちと一緒に一歩踏み出してみませんか?
▶PICK UP NEWS! OSPの多彩な活動の中から、特に気になる記事をピックアップします♪

OKINAWA SDGsプロジェクト(OSP、事務局・琉球新報社、うむさんラボ)は19日、那覇市の琉球新報ホールで「パートナーの集い」を開きました。パートナー企業14社から約30人が参加し、社会課題の解決を目指す事業や活動の結果生じた社会的、環境的な変化・成果を示す「社会的インパクト」について理解を深めました。
(1月20日公開)

「所得向上応援企業」に認証された県内34社はどこ? 従業員の待遇改善で評価 沖縄県とOSP
沖縄県は17日、積極的に従業員の待遇改善に取り組んだとして、県内34社を県所得向上応援企業に認証しました。
那覇市泉崎の琉球新報ホールで交付式を開き、照屋義実副知事が出席した各社代表らに認証状を手渡しました。
OKINAWA SDGsプロジェクト(OSP)との共同開催。第2部では「稼ぐ力」を主題に事例紹介やワークショップなどを実施しました。
(11月18日公開)

ジェンダー平等の実現へ組織内での男女共同参画の実行までのプロセスを学ぶ実践型講座が8日、那覇市の沖縄銀行本店内の「オキナワイノベーションラボ」で始まりました。計3回連続講座の1回目。7社から約20人が参加しました。
ファシリテーターをNPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの安谷屋貴子さんが務めました。
(11月9日公開)

食文化、米軍基地、海洋ごみ…修学旅行で「沖縄」考える 神戸の中学生、「OSPラーニング・ジャーニー」参加
修学旅行で沖縄を訪れている神戸大学付属中等教育学校(兵庫県)の3年生122人が3日、沖縄で社会課題解決を学ぶ「OSPラーニング・ジャーニー」に参加しました。
沖縄の食文化、米軍基地、海洋ごみ、赤土流出、生物多様性の五つのコースに分かれ、それぞれの課題解決に取り組んでいる企業や団体、地域住民などから話を聞きました。
(10月4日公開)

カフェや保育施設入居、公共施設の集客力で雇用生む 地域課題の解決例を紹介 OSP第1回カンファレンス
OKINAWA SDGsプロジェクト(OSP、事務局・琉球新報社、うむさんラボ)の第1回カンファレンスが14日、沖縄県那覇市の琉球新報ホールで開かれました。
「企業と自治体が共創し、地域の課題を解決するとは?」をテーマにした事例発表を聞いた参加者らは、自分自身やOSPのパートナー同士で実現できそうなことについて話し合いました。
(7月15日公開)

目指すは「沖縄らしい幸せな経済社会」 OSPが4期目キックオフ 企業の垣根越えSDGs推進
国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)を推進する企業・団体のネットワーク、OKINAWA SDGsプロジェクト(OSP、事務局・琉球新報社、うむさんラボ)第4期の開始となるキックオフイベントが16日、那覇市の琉球新報ホールで開かれました。
プロジェクトに加わる企業の関係者ら約70人が参加。沖縄らしい幸せな経済社会の実現に向け多様な意見を交わし合い、地域の課題を洗い出しました。
(6月17日公開)
「OKINAWA SDGs プロジェクト」とは…
「つなぐ」
各種勉強会やフォーラムを通して、企業と企業、ヒトとヒトをつなぎ、SDGsのプロジェクト化をお手伝いします。SDGsの17番目の目標である「パートナーシップで目標を達成しよう」を具現化し、連携して達成目標の実現に向け取り組んでいきます。
「伝える」
沖縄県内外のSDGsに関するニュースを発信します。企業や団体、地域の取り組みを発信することで、SDGsの機運を高め、「共感の輪」を広げていきます。
これまでの取り組み
お問い合わせ
琉球新報社 統合広告事業局 電話:098(865)5213(平日午前10時~午後5時)